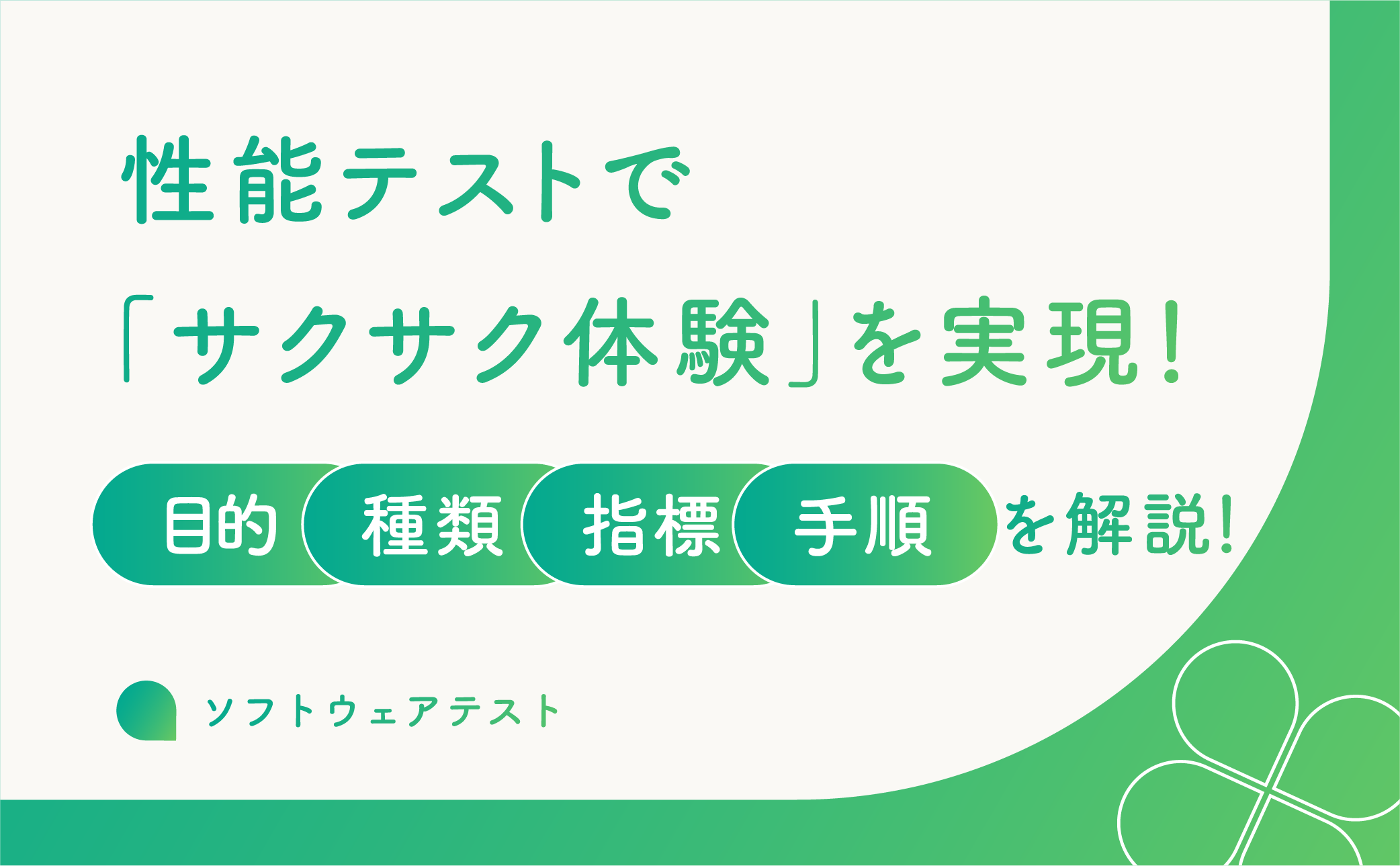機能テストとは丨定義と目的
機能テストとはアプリやシステムが、要件定義どおりに動くかをチェックするテストです。たとえばECサイトなら「購入ボタンを押したら商品がカートに入るか?」「カートから削除できるか?」など、ユーザーが行う基本操作が正しく動くかをひとつずつ確かめます。
見た目のボタンや画面遷移だけでなく、裏側で動いているデータベース処理、APIのやり取り、ログイン認証、サーバーとの通信なども対象です。ユーザーに提供する機能が開発目標どおりに機能しているかを広くチェックするのが目的です。
システムが正しく動作するかどうかを確認するためのアプローチ方法には、ホワイトボックステストとブラックボックステストの2種類があります。機能テストは、ブラックボックステストの一種です。
プログラムの論理構造が正しいかを解析するホワイトボックステストとは異なり、システムが正しく動くかを表面から確認します。内部のコードや構造を知らなくても、確認できるのが特徴です。入力(操作)に対して出力(表示や動作)がどうなるかに注目して確認します。
機能テストと非機能テストの違い
機能テストと非機能テストは、それぞれ確認する視点が異なります。機能テストは、仕様どおりに機能が正しく動くかを確認します。
一方、非機能テストは、動作の快適さや使いやすさ、安定性、セキュリティに注目します。「ログインに5秒かかる」「処理中にフリーズする」など、機能はしていてもユーザー体験に影響する部分をチェックします。
非機能テストは、機能テストほど目に見えにくいため軽視されやすい部分ではありますが、重要です。たとえ、アプリの機能がすべてそろっていても、動作が遅いまたは使いにくいと、クライアントの満足度は下がってしまうためです。
| 項目 | 機能テスト | 非機能テスト |
|---|---|---|
| 目的 | ソフトウェアが仕様どおりに正しく動作するか | 快適さ・安定性・安全性など、使いやすく安心して使えるか |
| 焦点 | 入力と出力、画面表示、機能の有無など | 処理速度、使いやすさ、耐久性、セキュリティなど |
| 主なテストの種類 | 結合テスト/総合テスト/受け入れテスト/回帰テスト | 性能テスト/負荷テスト/脆弱性テスト/UI/UXテスト |
| テスト観点の設定 | 比較的わかりやすい(仕様どおりかを見る) | やや難しい(使いやすさや快適さは主観を含むため) |
| クライアントの認識 | 正しく動くのは当たり前という前提 | 実装されていると好印象。気が利いていると評価されやすい |
機能テストはすべてのテストレベルで実施する
機能テストは一度実施して終わりではなく、開発の各フェーズで繰り返し行う必要があります。フェーズによってテストの目的や重要点が変わるため、初期段階からリリース直前まで実施することで品質を確保することが大切です。以下では、各開発フェーズでの機能テストの役割とポイントを解説します。
単体テストは、機能テストのなかで最初に行うテストです。モジュール単位で仕様どおりに動作するかを確認します。たとえば、ログイン画面なら「空欄時にエラーメッセージ が表示されるか」「ボタン表示が正しいか」など、個々の処理やUIの動作を確認するのが目的です。
欠陥を見つけた場合はその場で修正し、再度テストを繰り返します。このタイミングで欠陥を潰しておくことで、後工程での手戻りや影響範囲の拡大を防げます。
結合テストでは、単体で動作確認が済んだ機能同士をつなげて、連携が正しく機能するかを確認します。たとえば、ログイン処理の場合に次のような流れをまとめて確認します。
1.ユーザー名とパスワードを入力
2.入力値のバリデーションがとおるか
3.サーバーに認証情報を送信できているか
4.結果を受け取ってログイン完了画面が表示されるか
結合テストは単体テストでは問題ないものの、つないだ途端に欠陥が出るといったケースを防ぐために有効です。
完成したアプリ全体が要件どおりに動作するかを総合的に確認します。単体テストや結合テストではパーツ単位・機能同士のつながりを確認します。
一方、システムテストではユーザーが実際に使う状況を想定して、すべての機能を動かして問題がないかを確認します。たとえば、以下の内容を確認します。
・PCやスマホなど、複数のデバイスで正しく動作するか
・複数の機能が連携して、想定どおりのフローが実現できるか
・実行中に故障や予期しない挙動が発生しないか
問題があれば、要件どおりに動いていないことになるため、リリース前の最終確認としてとても重要です。
受け入れテストは、実際の業務で問題なく使えるか、ユーザーの立場で最終確認するテストです。設計どおりに作ったつもりでも、現場の業務フローにフィットしているか、直感的に操作できるかどうかは、実際に使わなければわかりません。
たとえば、注文システムで「入力がスムーズか」「操作ミスが起きにくいか」などを現場に近い環境でテストします。通常は発注者側が実施しますが、外部に依頼するケースもあります。
機能テストと関連が深いテスト活動
機能テストには、スモークテスト、健全性テスト(サニティテスト)、回帰テスト(リグレッションテスト)、ユーザビリティテストの4つの種類があります。ここでは、それぞれの特徴と役割をわかりやすく解説します。
スモークテストとは、新たに実装した機能や修正箇所が最低限動くかを軽く確認するテストです。たとえば、スマホアプリであればアプリが起動するか、ログイン画面が表示されるかなど、致命的な欠陥がないかを確認します。
万が一、この段階で「ログインできない」「アプリが落ちる」といった欠陥があると、細かいテスト以前の問題になるため、まず修正が必要です。この工程を挟むことで、後続のテスト作業の無駄を減らし、開発効率を高められます。
サニティテスト(健全性テスト)は、修正や新機能の追加後、該当箇所だけを絞って動作確認するテストです。たとえば、スマホアプリにチャット機能を追加した場合なら、以下のようなチャット関連の挙動だけを細かくチェックします。
・メッセージが送信・受信できるか
・通知が届くか
・チャット履歴が正しく表示されるか
リリース直前や修正直後など、要所だけ確認したいときに有効なテストです。
回帰テストとは、新しい機能の追加や修正を行った際に、既存の動作に影響が出ていないかを確認するテストです。開発現場では、一部を直したらほかが壊れていたというケースはよくあります。
想定外の巻き込み欠陥を防ぐために、過去に問題なかった処理をもう一度テストし直すのが回帰テストです。頻繁なリリースや修正が多いプロジェクトではとくに重要です。
ユーザビリティテストは、実際のユーザーの視点で「この画面は直感的に操作できるか」「情報が見やすく整理されているか」といった使いやすさを確認するテストです。とくに、業務システムでは、UIのわかりにくさが作業ミスや業務の遅延につながるため、操作性の確認が大切です。
分類上は非機能テストになりますが「使いにくい機能=実質使えない機能」となるケースも多く、機能テストと密接に関わります。機能が動くだけでなく、使える品質を担保するために不可欠なテストです。
機能テストを行う流れ
機能テストは、ただ項目をこなすだけでは不十分です。目的や対象に応じた手順を踏むことでテストの精度と効率が大きく変わるためです。ここでは、テストの事前準備から実行、結果の確認まで、開発現場で押さえるべき基本的な流れを紹介します。
「なぜテストを行うのか」「どの機能をどれくらい詳しく確認するか」そして「いつまでに終わらせるか」など、全体のスケジュールを考えてまとめるのが「テスト計画」です。これを作ることで、テストの内容や範囲が明確になり、チーム全体が迷わず効率的に動けるようになります。
ソフトやアプリの機能に求める動作をひとつずつ洗い出していきます。たとえば「ログインが正しくできるか」「入力したデータが正常に保存されるか」など、具体的に何をチェックするかを決める作業です。実際に使うユーザーの視点に立ちながら、できるだけ多くのポイントを見つけることが重要です。
観点が決まったら「正しいIDとパスワードでログインできるか」「間違ったパスワードで故障表示が出るか」など、確認ポイントを作ります。操作方法や期待される結果を詳しく書いておくことで、テスト中のミスを減らせます。
機能テストを始めるには、まずテスト専用のパソコンやスマホ、システムといった「テスト環境」を準備します。また、テストで使う「テストデータ」も準備します。ログインIDやパスワード、注文履歴など、実際の利用を想定したデータをそろえ、特殊文字入りのIDも用意しておくと便利です。
テストの準備が整ったら、いよいよ実際にテストを始めます。事前に作成したテスト項目に沿って、ひとつずつ操作しながら確認していきます。具体的には、手順どおりにソフトを動かし、期待している結果と実際の動きを比べて判断します。
発見した欠陥は速やかに開発側へ報告します。修正後は該当箇所に対して再テストを行い、対応状況を確認します。重要度に応じた優先順位づけやスケジュール調整も必要です。
【ユーザーアンケート】不具合改善がユーザー満足度に与える影響
株式会社NEXERとポールトゥウィンの共同調査では、アプリやソフトウェアを今まで使用してきたなかで「欠陥の改善スピードがユーザー満足度に影響する」と回答した人は8割を超えました。
「改善が遅いと信頼できない」「迅速な対応が企業の姿勢を示す」「欠陥放置は個人情報管理にも不安がある」「使う気がなくなりやすい」といった意見が多く挙がっています。
欠陥のない状態が理想ですが、リリース後の欠陥を完全に防ぐのは現実的に困難です。だからこそ重要なのが、問題をいかに早く見つけ、正確に修正できるかです。開発のスピードと品質を両立するには、ユーザー視点を意識した確認体制が欠かせません。
では、それを実現するために、どのように機能テストを進めていくべきか、次のセクションで解説していきます。
効果的な機能テストのポイント
機能テストを効果的に進めるには、計画性とタイミング、そして手法の工夫が欠かせません。ここでは、現場で役立つ具体的な機能テストのポイントを紹介します。
機能テストを効率よく進めるには、事前に「何をどうチェックするか」を明確に決めておくことが重要です。たとえば「パスワードを間違えた場合に正しくエラーメッセージ が表示されるか」など、具体的な確認ポイントを決めておくことでテストの精度と再現性が向上します。
機能テストは開発の終盤でまとめて行うよりも、できるだけ早い段階から段階的に進めると効果的です。開発初期からテストを実施することで、小さな欠陥やミスを早期に発見・修正でき、後からの大幅な手戻りやコスト増を防げます。
機能テストは一度だけでなく、開発の進行に合わせて何度もこまめに実施することが重要です。こまめにテストを行うことで「以前は正常に動いていたのに、知らないうちに欠陥が混入していた」といったトラブルを防げます。とくにアジャイル開発やDevOpsのような高速開発環境では、頻繁なテストが不可欠です。
効率よく機能テストを進めるには、自動化ツールの導入が効果的です。手動でひとつずつ確認するには時間がかかりますが、自動化すれば短時間で何度も繰り返しテストができ、ヒューマンミスも見つけやすくなります。
まとめ
機能テストは、ソフトウェアが仕様どおりに正しく動作するかを検証し、欠陥の早期発見と品質の安定化を図るための重要な工程です。
単体テストからシステムテストまで、開発フェーズごとに目的を持って実施され、入力と出力の整合性はもちろん、機能の連携や業務要件との適合性までを広く確認します。
性能やセキュリティといった非機能とは異なり、「正しく動くか」という基本的な信頼性を担保することに特化しているのが機能テストの特徴です。
機能テストを適切に設計・運用することで、後工程の手戻りを防ぎ、ユーザー満足度や製品への信頼向上にもつながります。
ただし、精度の高いテスト設計や継続的な実行には、専門的な知見や体制が欠かせません。
機能テストは、ソフトウェアが仕様どおりに正しく動作しているかを確認するテストです。入力に対して期待される出力や挙動をチェックし、欠陥を早期に発見することで、トラブルの防止につながります。
このテストは、性能やセキュリティといった「非機能」ではなく、あくまで機能そのものの正確さに着目している点が特徴です。単体テストからシステムテストまで、各開発フェーズで目的に合ったテストケースを設計・実行することが、品質向上のポイントです。
さらに、機能テストを通じて欠陥を迅速に修正することは、ユーザー満足度や製品への信頼にも直結します。スピードと品質を両立させるには、的確に問題を見つけ、素早く対処できる体制が欠かせません。
「リソースが足りない」「設計や自動化のノウハウがない」といった課題を感じている場合は、外部の力を借りるのも有効な選択肢です。
ポールトゥウィンは、検証業界歴30年の実績を持ち、テスト自動化の専門チームとして安定した技術をご提供します。数あるテストツールのなかから、お客様の課題に最適な内容をご提案するため、テスト効率の最大化が可能です。
自動テストの実施から保守、運用までの一括サポートで安心してお任せいただけます。
「品質向上を図りたい」「工数やコストを抑えて効率化したい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ポールトゥウィンでは、さまざまな業界・サービス・プロダクトにおいてテストの見ならず、品質向上の取り組みをサポートいたします。