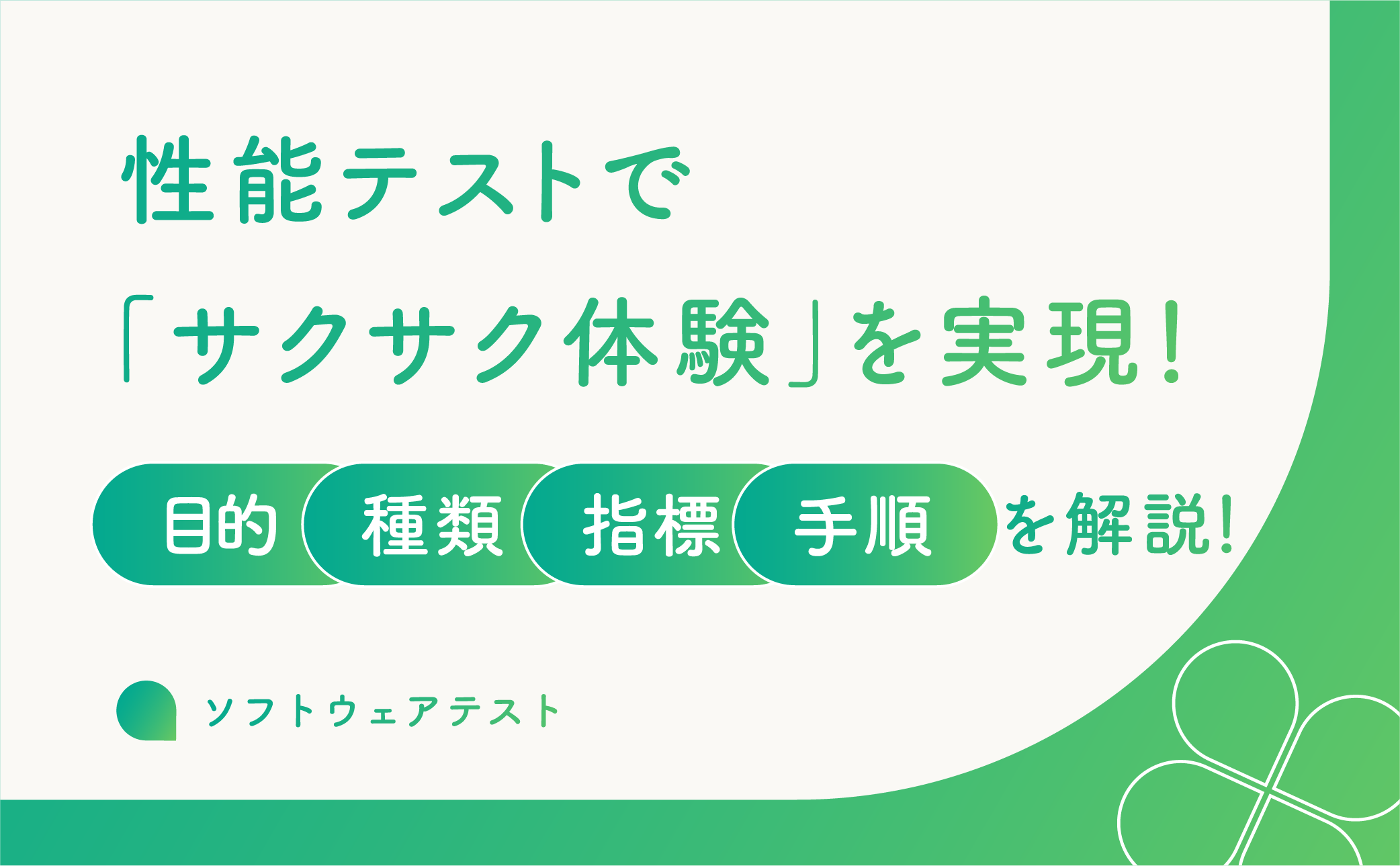シナリオテストとは
シナリオテストとは、実際のユーザーが行う操作の手順や流れを再現しながら、ソフトウェアの動作を確認する方法です。
「シナリオ」とは本来、映画や舞台における「脚本」を意味する言葉です。ユーザーが実際にどう使うかを想定した「ストーリー」を作り動作を確かめるため、操作のしやすさや画面の見やすさ、さらに使用中に起こる予期せぬ故障や使い勝手の問題まで、幅広くチェックができます。
シナリオテストの主な目的は「ユーザーがストレスなく利用できるか」を見極めることにあります。たとえシステムが仕様どおりに動作していても、操作が煩雑だったり画面の挙動に違和感があれば、ユーザーの満足度は低下してしまうでしょう。
そこで、実際の利用状況をできるだけ忠実に再現しつつ、以下のポイントを中心に検証を行います。
● 各機能がスムーズに連携しているか
● インターフェースやユーザー体験に不自然さがないか
● 実運用に近い環境で予期せぬ故障が発生しないか
ユーザー視点に立った操作フロー全体を確認することで、より実践的な品質チェックが可能です。
シナリオテストは、特定の段階だけで行われるものではありません。さまざまな開発フェーズにまたがって活用される柔軟なテスト活動です。そのため、ユーザーの行動パターンやサービスの利用目的をよく理解したうえで、現実的かつ網羅的なシナリオを作成するスキルが求められるでしょう。
シナリオテストとほかのテスト活動の違い
ここでは、シナリオテストと混同されやすいほかのテスト活動との違いを紹介します。
ユースケーステストは、ユーザーとシステムのやり取りを「ケース」として定め設計します。
ここでいうユースケースとは、利用者がどのような目的でシステムを使い、どのような操作を行うかを整理したものです。決められた条件や操作の流れに沿って、特定の機能が正しく動作するかを確認するため、限られた範囲や特定の場面に焦点を当てるのに適しています。
これに対して、ユーザーが実際に経験する操作の流れや、複数の機能が連携して動く様子に着目するのがシナリオテストです。ゲームのように複雑で多様な操作パターンがあるソフトウェアでは、シナリオテストによってユーザーの実際の行動に近い形で問題点を発見しやすくなります。
単体テストは、ソフトウェアを構成する最小単位(関数やモジュール)が、正しく動くかどうかを個別にチェックするテストです。小さなパーツごとに問題がないかを早めに見つけることで、後の開発作業がスムーズになり、製品全体の品質向上につなげられます。
一方、シナリオテストは、実際の使い方の流れを想定して、いくつかの機能や画面をまとめてチェックします。単体テストは部品単位、シナリオテストは使う流れ全体を見るテスト、と覚えるとわかりやすいでしょう。
結合テストは、単体テストを通過した複数のモジュールを組み合わせ、それぞれが正しく連携して動作するかを確認するテストです。主にモジュール間のデータの受け渡しやインターフェースの整合性といった「技術的な結合の正しさ」に焦点を当てます。
つまり、結合テストが「部品同士のつながり」を確認する工程であるのに対し、シナリオテストは製品としての完成度を見極める工程だといえるでしょう。
システムテストは、ソフトウェア全体をひとつの製品としてとらえ「きちんと仕様どおりに動いているか」を確認します。たとえば、ボタンを押したときに正しい処理がされるか、データが正しく表示されるか、スピードや安全性に問題がないかなど、さまざまな面から幅広くチェックします。
システムテストが「仕様への適合性」を広くチェックするのに対し、シナリオテストは操作感や使いやすさに重点を置いている点が大きな違いです。
【ユーザーアンケート】「使える!」と感じる改善とは?ユーザー目線のシナリオテストの重要性
導入するソフトウェアやアプリにおいて、操作の安定性や業務フローの円滑さは、利用者の満足度に直結します。
株式会社NEXERとポールトゥウィンが実施したアンケート調査によると「使用しているソフトウェアやアプリで、欠陥や問題が改善されたと実感したことはあるか」という問いに対し、約2割の方が「ある」と回答しました。改善された内容としては、以下のように業務に直結する動作の安定化や操作性の向上が多く挙げられています。
● フリーズがなくなった
● 特定操作での欠陥が解消された
● 通知表示やUIの誤りが修正され、操作がスムーズになった
ユーザーが製品やサービスに求めているのは、日常業務のなかで「使いやすい」「業務がラクになった」と実感できる、具体的な変化です。アンケート結果でも、体感できる改善こそが満足度や信頼感の決め手になっていることが明らかになりました。
加えて、約8割の回答者が「欠陥への対応スピードが企業への信頼に直結する」と回答しています。「対応が遅いと信頼を損なう」「迅速な改善は誠実な姿勢の表れ」といった声が多く、ユーザーは対応の早さにも高い期待を寄せていることがわかります。
ニーズに応えるためには、実際の業務フローに即した操作や状況を再現し、欠陥や使い勝手の課題を早期に発見できるシナリオテストの導入が欠かせません。業務の実態に即した検証を重ねることで、需要のあるソフトウェアを提供できるでしょう。
シナリオテストのメリット
ここでは、シナリオテストを実施するメリットを紹介します。
シナリオテストでは、実際のユーザー行動パターンにもとづいてシステムを評価できます。
「誰が」「どんな目的で」「どのように使うか」を丁寧に考慮しながら進めるため、操作のわかりやすさや迷いやすい部分など、開発者の視点では見落としがちな問題を発見しやすくなります。実際の利用場面を反映したテストを実施することで、ユーザーが快適に使い続けられるシステムに仕上げられるでしょう。
たとえ技術的に正しく動いても、業務の流れと噛み合わなければ現場での活用は難しくなります。だからこそ重要なのが、日々の業務を模したリアルな操作手順での検証です。
実務に即した視点で検証することで、「正しく動作するか」だけでなく、「業務で実際に役立つか」までを確認できます。
機能間の連携や画面遷移に潜む問題を見つけるのに効果的です。多くの処理は単体の機能だけで完結せず、複数の機能が連携して動いています。そのため、機能間のつながりにこそ、見逃されやすい欠陥が隠れていることが多いです。
たとえば「在庫確認 → 注文確定 → 支払い処理」という流れのなかで、在庫情報の更新がうまく反映されず、在庫ゼロでも注文が通ってしまうような問題は、機能をまたいだ流れのなかでないと発見できません。
複数機能の連携を含めた動作確認により、実際の運用に近い環境で品質をしっかりと保証できます。
利用者や管理者など異なる役割を持つユーザーが関わる一連の業務フローを通じて、それぞれの操作や情報の受け渡しが正しく機能しているかを確認できます。
たとえば、ECサイトでは、購入者が商品を注文した後、管理者が在庫管理や発送手続きを進めます。こうしたユーザー間の操作や情報の受け渡しがうまく噛み合っていなければ、誤配送や業務遅延につながりかねません。
異なるユーザーが関わる処理の連携がスムーズに機能しているかを事前に確認することで、サービス全体の信頼性向上に大きく寄与します。
シナリオテストは、プロジェクトに関わるすべての関係者が「システムがどう使われるべきか」を共有するための有効な手段です。
開発者、デザイナー、管理者、顧客など、立場の異なるメンバー同士でも、具体的な利用シーンをシナリオとして可視化することで、完成後の使われ方を同じイメージで捉えられるようになります。
たとえば「どの画面で何をするか」「どのタイミングで誰が操作するか」といった流れをあらかじめ擦り合わせておくことで、誤解やズレが減り、要件のブレや手戻りの少ない開発につながります。
シナリオを軸にコミュニケーションを図ることで、プロジェクト全体の方向性や目的が関係者全体で明確になっていくでしょう。
シナリオテストのデメリット
シナリオテストは実用性の高いテスト活動ですが、メリットだけでなく留意すべき課題もあります。ここでは、代表的な3つのデメリットを紹介します。
シナリオテストは、ユーザーの実際の操作を想定して検証を行うため、一つひとつのシナリオを個別に設計・準備する必要があります。そのため、テスト対象が増えるほど検証パターンが多岐にわたり、設計や実行にかかる工数が大きくなりがちです。
たとえば、同じ機能でも、利用者の立場や業務シーンが異なれば操作内容も変わります。それぞれに対応したシナリオを作るとなると、パターンの数は一気に膨れ上がります。
網羅的なテストは品質を確保するうえで重要ですが、実際にはすべてのケースを洗い出すのは現実的ではありません。そのため「頻繁に使われる操作」や「失敗すると影響が大きい流れ」に優先順位をつけ、現実的かつ効率的にシナリオを設計することが求められます。
シナリオテストは、あらかじめ定義された操作の流れにしたがって検証を行うため、想定外の使い方による欠陥には気づきにくいという課題があります。
通常、シナリオは「ある目的を達成するまでの一連の流れ」として、一本道で設計されます。そのため、ユーザーの誤操作や予期しない状況など、予定外の挙動には対応しづらく、実運用に近い問題を見落とすリスクがあります。
リスクを補うためには、シナリオのなかに例外的な条件や分岐パターンを意図的に組み込む工夫が必要です。ただし、あらゆる想定外のケースを洗い出すのは非現実的なため、発生頻度や影響度に応じて、優先度の高いパターンに絞ってテストするのが現実的なアプローチといえるでしょう。
シナリオテストでは、ユーザーの行動やシステムの仕様を正しく理解したうえで、的確なテストケースを作成するスキルが欠かせません。
開発経験が浅いテスターや、業務に詳しくない担当者がシナリオを設計しようとすると、本来検証すべき重要な観点を見落としてしまう可能性があります。また、テスト結果を正しく評価し、適切な改善策を立案するためにも、一定の経験と専門知識が求められます。
効果的に活用するためにも、経験や専門知識を持つ人材を適切に配置することが大切です。
シナリオテストでありがちな課題
シナリオテストは、実際の業務に近い形でシステムを検証できる有効な手段ですが、現場では「何をどうテストすべきか分からない」というつまずきがよく見られます。
よくあるのは、テスト観点が思い浮かばず、前任者の資料や古いシナリオをそのまま流用してしまうケースです。これでは、仕様変更や業務フローの変化に対応できず、意味のある検証とはいえません。
また「機能をとりあえず順に操作する」ような構成も、ユーザーの実際の利用を反映していないため、重要な不備を見落とす恐れがあります。
さらに、対象機能が多く、それぞれの仕様が細かく分かれていると、テストの設計はより難しくなります。機能ごとの動きを理解していても、組み合わせによって新たな検証項目が必要になるため、想定以上に手間がかかります。
加えて、仕様書が整備されていないケースでは、前提情報が曖昧なまま手探りで進めることになり、テストの目的自体があいまいになってしまう可能性もあります。
こうした課題を避けるためには、まず「シナリオテストとは何か」「何を検証したいのか」を明確にし、意図を持ってテストケースを設計することが重要です。
シナリオの作成方法
ここでは、シナリオを作成するための具体的な手順を、4つのステップに分けて紹介します。
まず、シナリオの起点となるアクター(ユーザーや関係者)を設定します。これは、誰がこの操作を行うのか、どの立場・役割で利用するのかを明確にする作業です。
採用担当者や経理担当者など、具体的な業務視点で設定することが重要です。
目的が定まれば、どこからどこまでをテスト対象とすべきか=シナリオの範囲も自然に決まります。
なお、目的の洗い出しは、アクター設定と同様に関係者へのヒアリングが重要です。開発側だけでなく、利用者の視点も取り入れることで、実態に即した信頼性の高いテストが実現できます。
シナリオは、目的をもとに「どんな場面で、誰が、何をするか」を具体的に書き出すことが大切です。このようにステップを細かく分けていくことで、どこで問題が起きるか、どう確認すべきかがはっきりするでしょう。
また、操作中のユーザーがどんな気持ちでいるか、どんな行動をとりそうかを想像することで、実際の利用シーンに近いシナリオに仕上がります。
■シナリオのサンプル①
以下のシナリオでは、ユーザーがECサイトで商品を検索し、購入手続きを完了するまでの一連の流れを確認します。
1. トップページにアクセスする
2. 検索ボックスに商品名を入力する
3. 検索ボタンをクリックする
4. 検索結果に該当商品が表示される
5. 商品Aの詳細ページに移動する
6. 「カートに入れる」ボタンをクリックする
7. カート画面で商品内容と数量を確認し、購入手続きへ進むを選択する
8. 決済情報や配送先を入力し、内容を確認する
9. 「注文を確定」ボタンをクリックする
10. 注文完了画面が表示される
11. 注文確認メールが届いていることを確認する
■シナリオのサンプル②
以下のシナリオでは、システムが想定外の入力や状況に対して、正しく制御・通知できるかを確認します。
「検索時の不正入力」
1. 検索ボックスに特殊文字を入力する
2. 検索ボタンをクリックする
3. エラーメッセージ が表示され、検索が実行されないことを確認する
「在庫切れ商品の購入」
1. 在庫が0の商品を選択する
2. カートに入れる
3. 購入手続きに進む
4. 「在庫切れのため購入できません」と表示されることを確認する
確認項目と期待値を整理するには、想定されるユーザーの行動や心理を踏まえ、操作によって情報がどのように変わるかを具体的に書き出すことがポイントです。
確認項目は、ユーザーの操作によって生じる目に見える変化や、確認が必要な状態を指します。たとえば、購入完了後にマイページの購入履歴に商品が追加されているかなど、具体的な変化をリストアップします。
期待値とは、確認項目に対して「どうなっていれば正しいといえるか」を示す基準です。期待値があることで、テスト実行時に結果の正否を判断しやすくなります。
なお、画面の遷移やボタン操作といった動作はテスト手順には含まれますが、確認項目ではありません。これらは機能テストで検証されるため、シナリオテストではユーザーが業務を進めた結果として「何が起きるべきか」に着目することが重要です。
網羅性が高いシナリオ作成のためのコツ
シナリオテストを有効に機能させるには、実際の業務やユーザー行動を広くカバーできるよう、網羅性のあるシナリオを設計することが欠かせません。ここでは、多様なユースケースに対応できるシナリオを作成するために大切な3つの視点を紹介します。
ユーザーの操作や業務の流れを、実際の利用順に沿って時系列で並べることで、抜け漏れを防げます。
ユーザーは、目的を達成するために複数の操作を段階的に行います。シナリオを時系列で構成することで、自然な流れのなかでどのタイミングで何が起きるかを正しく把握でき、業務全体の整合性も確認できるでしょう。
システムの挙動は、設定内容や利用条件によって変わるため、条件ごとにシナリオを分けて設計することが大切です。
たとえば、会員か非会員か、入力ミスの有無、設定の違いなどによって、処理の流れや表示結果が分岐します。パターンを押さえるには、過去の操作履歴や問い合わせ内容、顧客からの要望を活用するのが効果的です。
条件ごとに整理されたシナリオは、欠陥の傾向をつかみやすくし、テスト後の分析や改善にも役立ちます。
すべてのパターンを網羅できれば理想的ですが、時間や人手には限りがあります。システムがユーザーにもたらす価値や、顧客の目標に直結する部分を優先的に選び、効率的にテストを進めましょう。
優先順位をつけることで、リスクの高い箇所を優先的に確認でき、限られたリソースでも効果的な品質向上が期待できます。
シナリオ作成時の注意点
ここでは、シナリオ作成で気をつけたいポイントを紹介します。
シナリオ作成は、ユーザーがどんな目的や課題を持っているかを理解してから始めましょう。利用者の視点に立つことで、実際の利用場面に即したシナリオが作成できます。
シナリオの粒度を適切なレベルに設定することが、効率と効果を高めるポイントです。
細かくしすぎると確認項目や手順が増え、作成・管理の負担が大きくなり、テスト実施者の負荷も増加します。一方で、大まかすぎると問題の特定が難しくなるため、バランスが重要です。
必要な範囲をまとめ、重要な流れをしっかりカバーすることが大切です。
システムやソフトウェアを運用する際は、正しい操作だけでなく、入力ミスや誤操作といった予期しない行動も起こり得ます。ひとつのテストケースに対して、想定外の操作も考慮し、欠陥を見逃さないようにテストを行うことが重要です。
実際の業務に合わせて多様な操作パターンを取り入れると、確認項目や手順が細かく複雑になりがちです。担当者が交代しても混乱なく引き継げるよう、テスト手順や操作方法、期待される結果を明記したテスト仕様書の作成が重要です。
実際にシステムを使うユーザーの意見を取り入れることで、開発者だけでは気づきにくい不備や使い勝手の課題が明らかになります。過去のトラブル事例や操作ミスなども参考にしながら、ユーザー視点での改善点を抽出し、シナリオに反映させていきましょう。
まとめ
シナリオテストは、ユーザー満足度を大きく左右する重要な工程です。ユーザーの操作を具体的に想定し、さまざまなケースを網羅してテストすることで、リリース後のトラブルを未然に防げます。
ただし、シナリオの設計には一定の手間と専門的な知識が必要なため、自社だけで対応するのが難しいケースも少なくありません。シナリオテストでお悩みある方には、専門家に相談することをおすすめします。
ポールトゥウィンは、JSTQBプラチナパートナーとしての高い専門性と、30年以上にわたる豊富な実績を活かし、ソフトウェアテストを提供しています。Webサイト、モバイルアプリ、IoT機器など幅広い分野での検証実績があり、お客様の業界特性やプロダクトの特性を踏まえ、テスト計画の立案から実行まで一貫してサポートいたします。
600機種以上、5,000台以上のスマートフォンやPC、さまざまな新旧OSなど、多様なテスト端末を完備しています。また、多数のテスターが在籍しており、お客様のご要望に応じて、常駐やラボ型⽀援、テレワークでの検証など、ご要望に合わせた稼働が可能です。
シナリオテスト設計に不安を感じている方は、お気軽にポールトゥウィン株式会社へご相談ください。