業界全体の成長を目指して 経験を力に変える勉強会
2025年4月、ポールトゥウィン株式会社(PTW)の新宿オフィスにて、ゲーム業界で日々ユーザー対応に携わるカスタマーサポート(CS)担当者による座談会が開催されました。
この座談会は、現場で得た実体験を持ち寄り、互いに学び合う“実務者同士の勉強会”として企画されたもので、一般社団法人コンピューターエンターテインメント協会(CESA)に加盟する企業をはじめ、業界内で連携のある複数の企業が参加しました。CESAは、日本のコンピューターエンターテインメント産業の健全な発展を目的に設立された業界団体で、家庭用ゲームやモバイルゲーム、オンラインゲームを提供する多くの企業が加盟しています。ポールトゥウィンもこのCESAに長年参加し、加盟企業同士の交流や意見交換を重ねてきました。
今回の座談会は、そうした日常的なつながりを背景に、カスタマーサポートの最前線に立つ者同士が、 “リアル“な体験を持ち寄り、お互いの現場に役立てることを目的として企画されたものです。
カスタマーサポートの仕事は、ユーザーの声と最も近い場所で行われ、トラブル対応やサービス運用の改善など、ゲーム体験の信頼性を支える役割を担っています。そうした現場では、様々な経験を通じて得た “気づき”こそが、チームやサービスを前進させるきっかけになることも少なくありません。
そこで今回の座談会では、「現場にこそ、本当の学びがある」をメインテーマとし、実務での課題や試行錯誤の中で得られた教訓を率直に語り合う勉強会形式で進行しました。共通する悩みや工夫を共有することで、業界全体の知見とサービス品質の向上につなげることを目指しています。
主催を務めたPTWの鈴木と、司会進行を担った株式会社WFSの佐野様もまた、「他社の経験を自分たちが繰り返さない。自分たちの経験も、他社の学びにしてほしい」という共通の想いをもって本会を立ち上げました。佐野様は冒頭の挨拶で、「そういった意識の共有が、より良いサービスづくり、さらには業界全体のレベルアップにつながっていく」と述べ、こうして集まったご縁への感謝と、この取り組みへの意義を参加者と共有しました。
マニュアル通りにいかないCSの現場だからこそ、実際に向き合ってきた担当者同士が、実情をありのままに語り合える機会には大きな意味があります。ポールトゥウィンとしても、こうした率直な意見交換の場を持てたことは非常に意義深く、現場にとって確かな学びと手応えを得られる時間となりました。
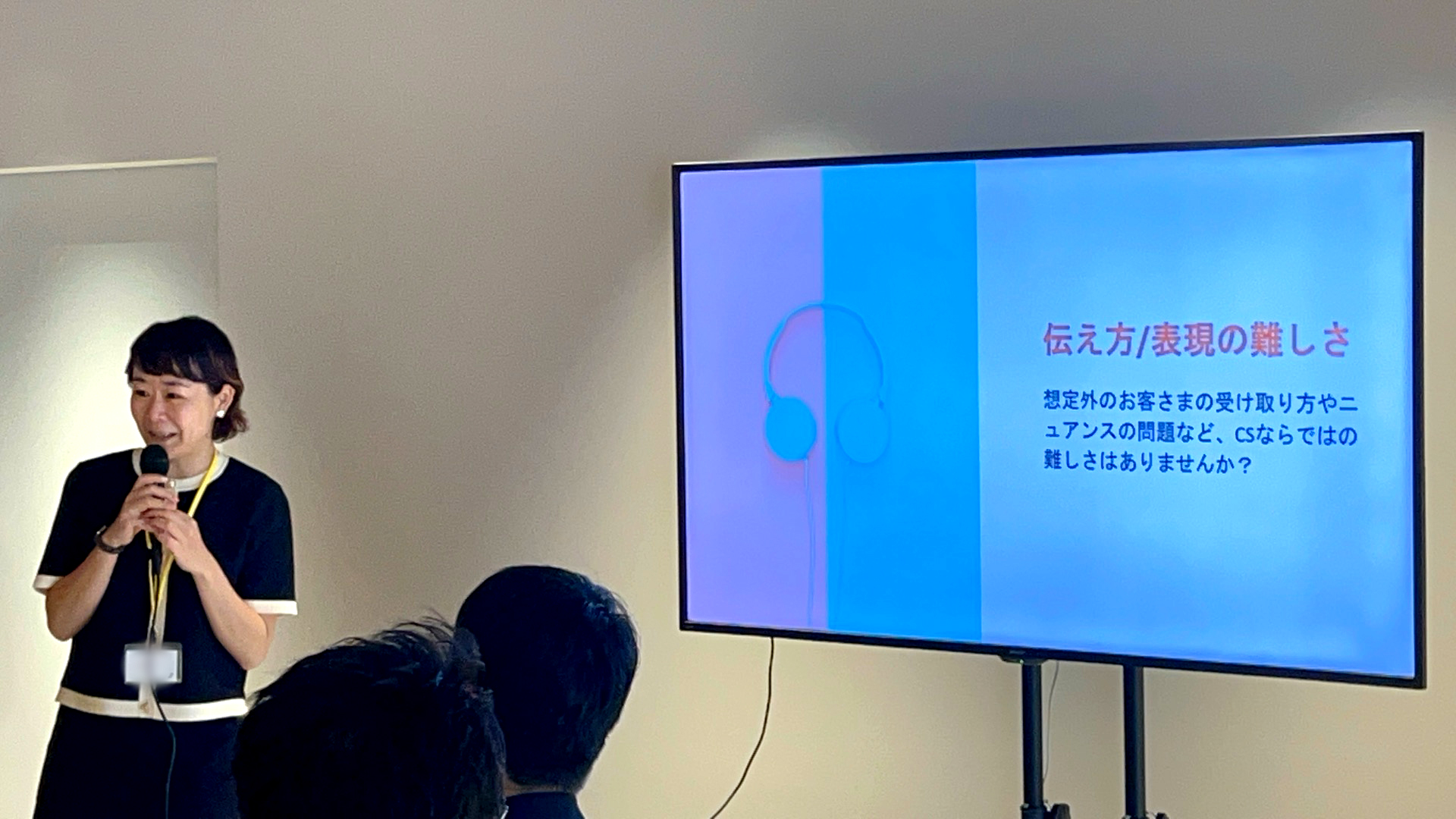
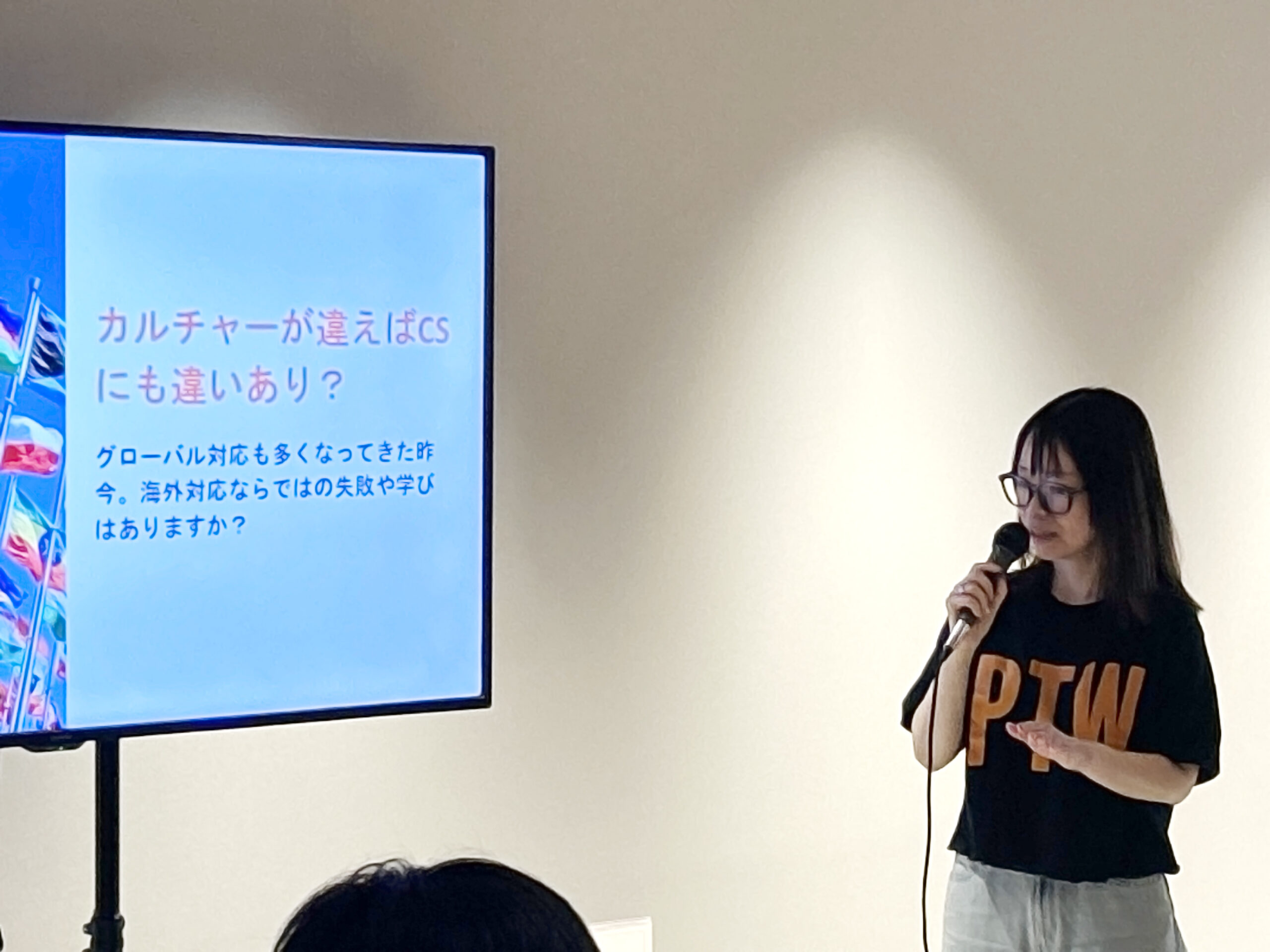
リアルな現場から学ぶ事例と教訓 テーマ別ディスカッション
今回の座談会では、「現場にこそ、本当の学びがある」というテーマに沿って、複数のディスカッションテーマが設けられました。各テーマに対して複数の企業から発言があり、それぞれが過去に直面した課題や対応の工夫、そこから得た気づきについて率直に共有されました。参加者同士が深く頷き合い、共感や新たな視点が生まれていたのが印象的で、どのエピソードも“現場ならでは”の学びに満ちていました。

ユーザーとの信頼関係は、対応の正しさだけでなく、「どう伝えるか」「どう判断するか」によって大きく左右されます。このパートでは、言葉選びの難しさや、善意が裏目に出る補填対応の事例を通じて、CSにおける信頼構築の本質が見えてきました。
最初のテーマは、「伝え方/表現の難しさ」でした。日々サポートの現場でお客様と向き合う中で、誰もが一度は悩むテーマです。
過去のトラブル対応を振り返る中で、ある参加者からは「お詫び文に『今後は絶対に同様の問題が起きないようにします』と記載した直後に、再び問題が発生してしまった」というエピソードが共有されました。この経験を通じて、確実に実現できる保証がないことについて断定的な表現を使うことの危うさが指摘されました。対応時の言葉選びには細心の注意が必要であり、「丁寧な姿勢は重要であっても、根拠のない断言は信頼を損なうリスクがある」との意見が出されました。
こうした意見交換を通じて、言葉の持つ重みと責任について改めて考える機会となり、表現一つひとつに配慮する姿勢の重要性が共有されました。
続くテーマは、「良かれと思ったのに…」です。カスタマーサポートの現場では、お客様のためを思って取った行動が、かえって裏目に出てしまうことがあります。今回は、そうした善意から生まれた思わぬトラブルの事例が共有されました。
あるケースでは、不具合に関する問い合わせが複数寄せられた際、申告のあったユーザーにのみ個別に補填を行った結果、想定を大きく上回る数の問い合わせが殺到し、対応が混乱したというエピソードが紹介されました。補填内容を明示的に告知しなかったため、補填対象外のユーザーからも同様の対応を求める声が相次ぎ、結果として運用全体に影響を及ぼしました。
このような経験から、透明性や公平性を欠いた個別対応は、たとえ善意であっても不信感や混乱を招くリスクがあることが改めて認識されました。補填ルールや運用方針は、あらかじめ丁寧に設計し、わかりやすく伝えることの重要性が強調されました。
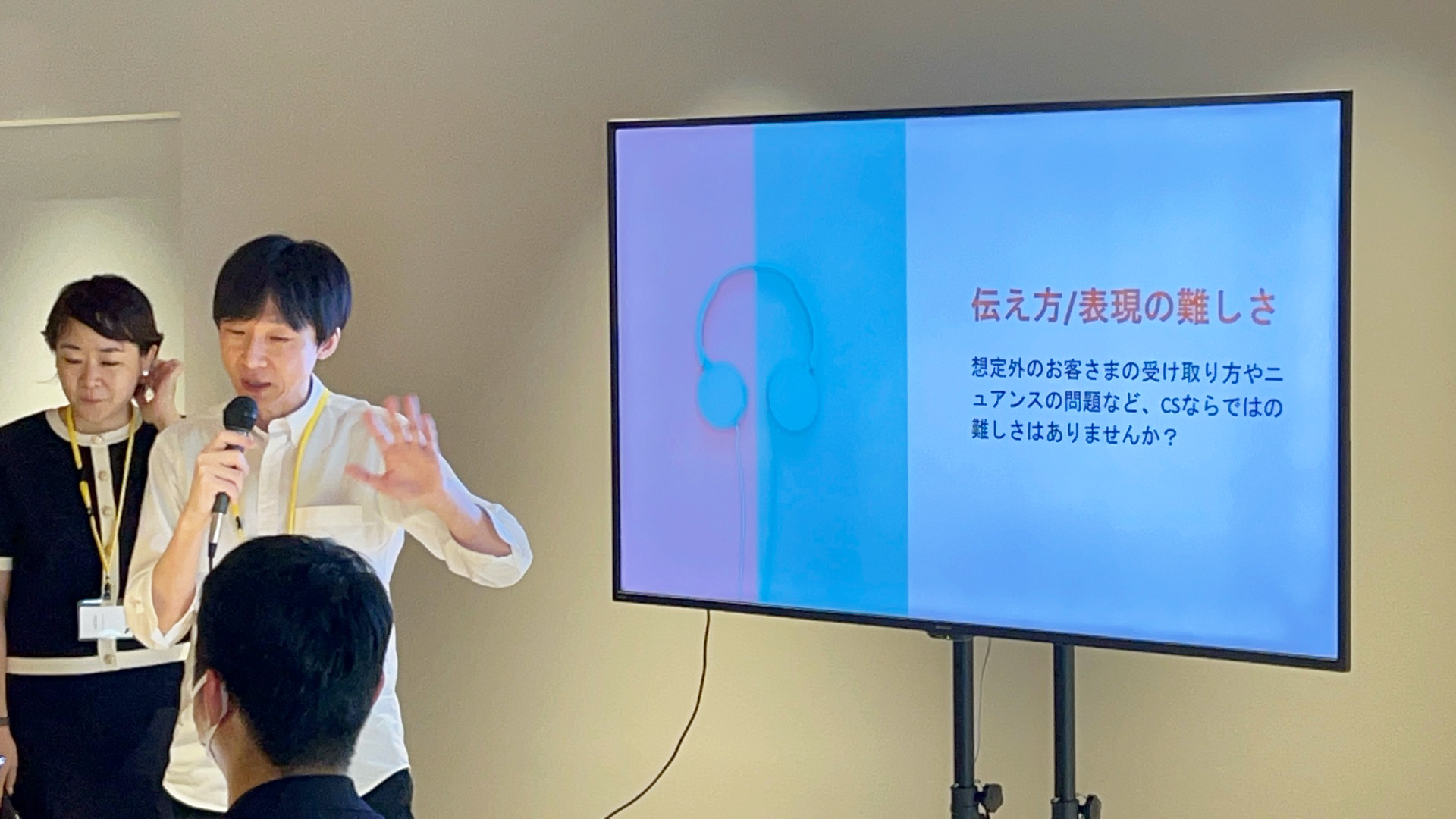
CSの現場では、日々のオペレーション設計からグローバル展開まで、柔軟かつ精度の高い対応が求められます。このパートでは、効率化が裏目に出た事例や、文化の違いが引き起こす認識のズレを通じて、運用設計や連携における“見えにくい落とし穴”と、そこにどう向き合うかが語られました。
続くテーマは、「ザ・オペレーション!」です。日々のカスタマーサポート業務では、複雑なオペレーションをいかに正確かつスピーディに回すかが重要とされています。しかし、その設計や運用の中には、思わぬ落とし穴が潜んでいることも少なくありません。
ある事例では、対応スピードを向上させる目的でフローの細分化を進めたところ、確認事項が過度に増えてしまい、新たに加わったスタッフの習得に時間がかかるという副作用が生じたといいます。「現場の効率化を目指して整備した仕組みが、結果的に負担になってしまった」という声もあり、スピードと精度のバランスをどう保つかの難しさが語られました。
さらに、過去には業務が担当者の頭の中だけに留まっており、ドキュメント化が不十分だったために、緊急時の対応が遅れたという反省も紹介されました。こうした教訓を踏まえ、現在では細かな業務フローまでしっかりと文書化し、日常の運用に活かす取り組みが進められています。
4つ目のテーマは、「お客様のいるところにCSあり」です。リアルイベントやオフライン施策の現場では、オンライン対応とは異なる難しさや判断の難所が存在します。今回は、そうした場面で実際に起きた課題や事例が共有されました。
ある発表では、会場設営の都合により一部の観客の視界が遮られるという問題が発生し、現場で柔軟に席の移動対応を行った結果、他の参加者との間で不公平感が生じたというケースが紹介されました。対応そのものは来場者の利便性を考慮したものでしたが、その副作用として公平性のバランスを崩す結果となってしまいました。
こうした事例を通して、リアルな現場における対応では、スピードや柔軟性だけでなく、常に「公正さ」や「受け手の想いへの配慮」が求められることが改めて浮き彫りになりました。とくに、社員だけでなくアルバイトや外部スタッフが関わる体制においては、対応基準の統一と周知の徹底が極めて重要であるという認識が共有されました。
最後のテーマは、「カルチャー違えばCSにも違いあり」でした。グローバル対応が当たり前になりつつある中で、国や文化によって異なる価値観や働き方が、カスタマーサポートの現場にも大きな影響を及ぼしているという実情が語られました。
海外チームとの連携においては、時差の問題以上に、文化の違いに起因するすれ違いや摩擦が課題として挙げられました。たとえば、日本では控えめで協調を重んじるコミュニケーションが好まれる一方で、他国では自己主張を前提としたスタイルが一般的であることから、やり取りの中で感覚のずれが生じることがあるとの意見が共有されました。納期に対する意識の違いや、報連相(報告・連絡・相談)のあり方にギャップを感じることも少なくないといいます。
また、国内で求められる高い応対品質をそのまま海外チームにも適用しようとした結果、意図しない摩擦が起きることもあるという声もありました。言語の壁や文化的背景の違いが要因となり、改善の方向性がうまく定まらないといった悩みも共有されました。

支え合い、学び合う関係へ 懇親会の様子
座談会のあとは、立食形式の懇親会が開かれました。
食事やお酒を片手に、参加者たちは自然と輪を広げ、知り合い同士はもちろん、初対面の人同士でもすぐに打ち解けていきました。仕事の話からプライベートの話題まで、自由で和やかな交流が続き、笑顔や笑い声が絶えない温かなひとときとなりました。座談会で共有された「互いの会社の経験を学び合う」という想いが、この時間を通じて信頼関係や横のつながりへと形を変えていった印象的なひとときとなりました。

おわりに
今回の座談会は、日々の現場で悩みながらも、より良いCSを目指して試行錯誤する担当者たちが、“現場経験”をキーワードに本音で語り合う貴重な場となりました。
ポールトゥウィンとしても、こうした率直な意見交換を通じて、現場が抱えるリアルな課題に触れることができ、非常に実りある時間だったと感じています。そして、このような機会をともに作ってくださった登壇企業の皆さま、お忙しいなか足を運び、実際に起きた出来事や学びを惜しみなく語ってくださった参加者の皆さまへ、心より感謝申し上げます。
今後も、CS現場の知見が企業を越えて循環し、業界全体のサービス品質向上と、ユーザーが安心してゲームを楽しめる環境づくりが広がっていくことを願っています。









